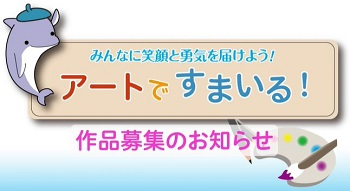回復を促す家族の接し方
病気の段階ごとに対応のポイントをまとめましたので、参考になさってみてください。
統合失調症の回復のためには、ご家族の協力が大きな助けになります。 病気を発症された当初は、ご家族も動揺したり混乱されることがあると思いますが、そんな皆様のために、病気の段階ごとに対応のポイントをまとめましたので、参考になさってみてください。
監修:白石弘巳 先生
埼玉県済生会なでしこメンタルクリニック院長
東洋大学名誉教授
1.はじめに知っておいていただきたいこと
参考ページ:家族の支援ガイド 5.家族の対応ABCはこちら
1.はじめに知っておいていただきたいこと
病気になったのはだれのせいでもありません
統合失調症は、約100人に1人がなる可能性のある身近な病気で、脳内の情報を伝える神経伝達物質のバランスがくずれて起こります。本人がなにかをしたから発症したわけではなく、親の育て方や遺伝のために起こるわけでもありません。ご家族がご自身を責めたり、本人の将来を悲観したりする必要はありません。
「家族は味方」というメッセージを送りましょう
統合失調症を発症した人は、今までに体験したことのない不安を感じています。幻覚(幻聴など)や妄想により周囲への不信感が増し、閉じこもりになりがちですから、まずご家族が「私たちはあなたの味方」というメッセージを送ってあげることが大切です。
回復に向けたイメージをもって接しましょう
家族の理解と接し方が治療の進み方に大きな影響を与えます。病気の症状や正しい治療法を理解し、回復に向けたイメージをもちましょう。病気の見通しや最善の効果をあげる方法を知ることで、安心とゆとりが生まれます。回復に向けたイメージをもつことは、本人にとっても大切なことです。

相互理解と信頼が何より大切
幻聴や妄想など、回復を妨げている症状をできるだけ取り除くことが本人の悩みや苦しみを減らすことになります。まずはさまざまな症状に苦しむ気持ちに寄り添いましょう。そして苦しみを取り除く治療方法があることをわかりやすく、やさしく説明しましょう。

薬物療法と非薬物療法を組み合わせて
統合失調症の治療は抗精神病薬による薬物療法が欠かせません。しかし、薬物療法だけでは幻覚や妄想などの症状が完全には消えなかったり、病気による生活のしづらさが残ったりすることが少なくありません。そのため、統合失調症の治療は、薬物療法に加え、社会生活する上で必要な日常生活や対人関係に関する技術の向上、就職に必要なスキルの開発など、生活のしづらさを改善して社会参加を促す「精神科リハビリテーション」を組み合わせるとより高い効果が期待できます。
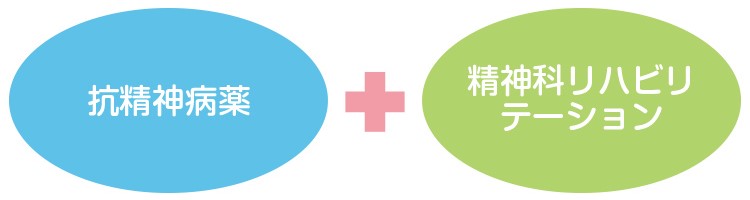
主治医とのコミュニケーションが治療効果に反映
統合失調症は長い経過の慢性疾患ですので、医師-本人-家族の連携が欠かせません。医師は症状と薬の効果・副作用、日常生活の中での不安や困りごとなど、さまざまな情報を元に治療を調整しています。気になることがあればなんでも主治医に伝えましょう。言いたいことや聞きたいことをメモにまとめておくと良いでしょう。

多くの専門スタッフが協力して治療を進めます
医療機関では、医師や看護師だけでなく、精神科ソーシャルワーカー(PSW)、作業療法士、臨床心理士、薬剤師や栄養士など、多くの専門スタッフが働いています。より良い効果を得るために、これらのスタッフが本人の希望を確かめながらチームで治療を進めていきます。