脳科学から見た統合失調症
統合失調症を科学的な視点から解説しています。
監修:仙波純一先生
さいたま市立病院
4.統合失調症の遺伝子研究
4-1統合失調症での“遺伝”の意味
この章では統合失調症の遺伝子研究を紹介しようと思います。
統合失調症に限らず、最近の医学研究では病気に関係する遺伝子の探求やその機能の解明が精力的に行われています。
ところが、一般の人が考えている“遺伝”や“遺伝子”の概念と、医学専門家が使う“遺伝”の意味は少しずれているところがあるようです。
この点をまずこの章を始める前に説明しておきましょう。
そうしないと、精神病の遺伝子研究というと、すぐに“精神病は遺伝するのか“と早とちりされかねないからです。
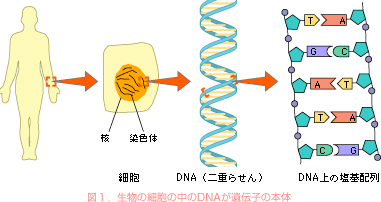
【図1】生物の基本単位である細胞内には、染色体とよばれる構造物があります。
染色体の中ではDNA(デオキシリボ核酸)とよばれる長い分子が二重のらせんを形成しています。
このDNAにはA(アデニン)、
C
(シトシン)、G(グアニン)、T(チミン)とよばれる分子(塩基)が図のように連なっています。AとC、GとTが結合するので、ちょうど二本のらせんとなるのです。
遺伝子というのは、親から子に伝わり生物のいろいろな性質を決定する因子として想定されていたものです。 みなさんも中学生のときにメンデルの遺伝の法則を習われたことでしょう。 1953年に、遺伝子は細胞の染色体にあるDNA上にあり、それぞれAGCTとよばれる塩基配列で表される情報として存在していることがわかりました(図1)。 ここから現在の分子遺伝学が始まったといってよいでしょう。 このように遺伝子は親から子へ伝わるという“遺伝”を媒介する役割を果たしています。 一方で、遺伝子はヒトの設計図としての役割も果たしています。 人の身体にある細胞すべてに同じ遺伝子の集団(これをゲノムといいます)が存在しています。 それぞれの細胞では、それぞれの役割に応じた遺伝子が必要な時期に応じて活躍していて(“発現している”といいます)、それ以外の遺伝子はお休みしています。
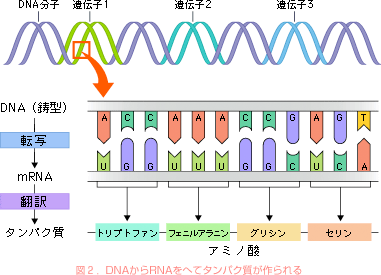
【図2】DNA分子は2本の長い分子が2重のらせんを作っています。
遺伝子はこのDNA上に並んでいます。DNAにあるACGTの情報はRNA(リボ核酸)に移され(転写)、このRNAの情報をもとにアミノ酸が作られていきます(翻訳)。
アミノ酸が連なってタンパク質が作られます。4種類の塩基のうちの3つの並び方で、一つのアミノ酸が決定されますので、このしくみを遺伝子の暗号の解読とよぶことがあります。
先にお話ししたように、遺伝子の情報はDNA上の塩基配列として表されています。図2に示したように、DNAの情報はRNAに移され、さらにこのRNAが設計図のコピーとなってアミノ酸が作られていきます(AGCTの4つの塩基のうち、3つの配列の仕方で一つのアミノ酸が表されます)。
このアミノ酸が連なったものがタンパク質となります。
タンパク質は酵素など細胞内で活躍する重要な物質です。
生体内の細胞はひとつひとつ自分の役割に応じた遺伝子を発現させ、いろいろな種類のタンパク質を作っていきます。
このタンパク質が細胞内の他の生体分子や、あるいは他のタンパク質と相互作用しながら、生体内のダイナミックな働きが営まれていきます。
ヒトゲノム計画が完了し、ヒトの遺伝子は約3万と推定されました。
生物の多様な働きを考えると、もっと遺伝子はたくさんあると予想されていました。
実際の予想より少なかったのは、遺伝子はタンパク質と結合し、さらにそのタンパク質は種々の修飾を受けて、多くの段階で遺伝子の発現を調節するので、数はそれほど多くなくとも、多様な生命活動を維持できるためといわれています。
このように遺伝子が細胞内で実際に働き始めるのにはたくさんの働きを調節する因子があります。
この仕組みをエピジェネティックス(epigenetics)とよび、最近の分子遺伝学の重要なテーマの一つになっています。
病気の遺伝子でいうと、その遺伝子を持っていればただちに病気になるというのではなく、遺伝子が働き始めるには、多くの調節する因子があるということです。
それが解明できれば病気の治療にも役立つはずです。今後の発展が期待される分野です。
4-2-1統合失調症での“遺伝”の意味
先に述べた遺伝子の働きから考えると、遺伝子の働きに障害があれば、何らかの病的な状態が引き起こされそうだということも理解できるでしょう。
しかし、ほとんどの病気はその仕組みがよくわかっていません。
そこで、最初に病気を引き起こす遺伝子を見つければ、その後の研究に大きな力となります。
医学研究者が病気の遺伝子探しに熱中する理由の一つはこれにあります。実際、今まで遺伝子疾患とよばれている病気のなかで、ハンチントン舞踏病、あるタイプの筋ジストロフィー、のうほう性線維症などの原因遺伝子が見つけ出されています。
しかし、すべての病気が必ずしも遺伝子の異常だけで説明できるわけではありません。
たとえば、先に述べたハンチントン舞踏病などは、一つの遺伝子の異常によって生じることがわかっています。
これらは単一遺伝疾患とよばれます。
これに対して、多くの遺伝子が関係していて、一つの遺伝子の異常だけでは病気は起こらない病気を多因子疾患といいます。
統合失調症は本態性高血圧、糖尿病、ぜんそくなどとおなじような多因子疾患です。
また、ヒトの病気のほとんどは、実際は多くの遺伝子と多くの環境との相互作用のなかから発病してきます。
たとえば、糖尿病や高血圧などは、なりやすさが遺伝するために、両親がこれらの病気にかかっていると、発病しやすいという事実はご存じでしょう。
しかし、それでも本人が糖尿病や高血圧にならないような食事や生活を送っていれば、発病しないこともあります。
つまり、病気そのものが遺伝するのではなく素因(なりやすさ)が遺伝するといってもいいでしょう。
この素因はスペクトルのように、ある人が精神疾患にかかりやすい側から、かかりにくい側まで連続的に広がっています。
その意味で、この素因は程度の差はあれだれでも持っているものです。
4-2-2統合失調症における遺伝と環境の役割
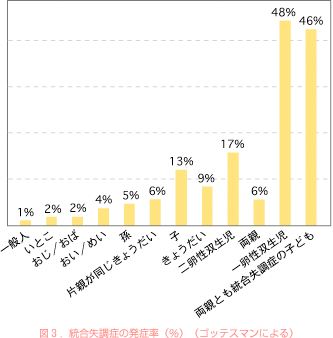
【図3】家系の誰かが統合失調症の場合、本人が統合失調症を発症する危険率を示したものです。
たとえば、本人のいとこが統合失調症であると、本人が統合失調症を発症する割合が2%と推測されます。
統合失調症の一般での発症率は1%弱です。
統合失調症のなりやすさは親から子へと伝わっていきます。
したがって、親が統合失調症であると、子どもも統合失調症になる危険率は確かに上昇します。
図3に示したように、両親のどちらかが統合失調症の場合、子供が統合失調症になる危険率は約6倍になるとされます。
ここで6倍というと、とても大変な数字のように思われるかもしれません。
しかし統合失調症の一般での発病率は1%弱ですから、親が統合失調症でも94%の人は統合失調症を発病するわけではありません。発病率はあくまでも比率であることを銘記してください。
一卵性双生児の場合、遺伝子はほぼ同一です。一卵性双生児の一方が統合失調症である場合、もう一方が同じ病気である率は50%であるといわれています。
遺伝子が同じであると発病率はかなり高くはなりますが、100%ではないことをみると、個人差や環境要因も発病に関連していることを示しています。
また、きょうだいだと生育環境も同じになるので、同じ病気になりやすいのではないかと考える人がいるかもしれません。
しかし、生後直ちに別々の家庭で育てられた一卵性双生児の研究(養子研究)でも、同じくらいの発病率が報告されていますので、やはりすべてを環境要因のせいにはできません。
また、環境要因にしても、これが決定的な発病要因となるというものは見つかっていません。
むかし悲惨な母子関係が統合失調症の子どもを作るという説がありましたが、これは現在では否定されています。
また、ここでいう環境因子というのは、遺伝的な因子以外のすべてを指しています。
したがって、その人の住む地域環境、家庭内環境、友人関係、経済的状況、教育歴などにとどまらず、その人が生まれる前の母胎の状況、かかったことのある病気なども含まれています。
4-3統合失調症の遺伝子研究-関連研究と連鎖研究

病気に関連する遺伝子の研究は、関連研究や連鎖研究などの方法で行われます。
関連研究はあらかじめ関連が疑われる遺伝子を患者さんと対照群で調べます。
もし、患者さんのほうにその遺伝子が多ければ、その遺伝子そのものかあるいはその近くにある遺伝子が、疾患に関係する遺伝子(疾患遺伝子)であろうと想定します。
同じ遺伝子でもその中にある小さな塩基配列が異なっていたり(これを遺伝子多型といいます。
血液型のABOもその一種です)、あるいは同じ塩基の繰り返しの回数が異なっていたりすることがあるので、これを利用します。
この研究方法では、発症に関わってはいてもそれほど関与が強くない遺伝子でも見つけることができます。
研究の初期には、第2章で述べた統合失調症のドーパミン仮説に基づいて、ドーパミンの受容体・合成酵素・分解酵素などの遺伝子が調べられました。
そのほかに脳の情報伝達に関連しそうな多くの遺伝子が調べられましたが、それ一つで統合失調症の発病を決定するような大きな影響力を持った遺伝子は見つかっていません。
せいぜい、その遺伝子を持っていると発病率が少し高くなったり、逆に低くなったりする程度の影響力を持った遺伝子が見つかっているくらいです。
一方、連鎖研究はDNAマーカーとよばれる染色体上の位置を示すしるしを使って、マーカーと疾患遺伝子との位置を解析し、疾患遺伝子の染色体上の位置を探し当てる方法です。関連研究と違って、疾患遺伝子はあらかじめわかっていません。
この方法では、疾患遺伝子のおおよその位置がわかるので、その後その区間にある遺伝子を探していくことになります。
この研究を行うためには、多数の患者さんとそのきょうだいや両親からの遺伝子を調べさせてもらう必要があります。
現在世界で広く行われており、わが国でも独自の研究が多くの大学や研究所が協力して行っています。
今のところ、ある程度統合失調症の発症に関連している染色体上の領域が示唆されています。
しかし研究グループごとにその結果は一致せず、まだ研究は途中の段階です。
関連研究の結果と同様に、統合失調症に関係する遺伝子はあるかもしれないが、発病を決定づけるような大きな影響のある遺伝子は見つかっていません。
おそらく、これからもそのような決定的な疾患遺伝子は見つからないと思われます。
しかし、ひとつひとつの遺伝子はそれほど強い関係を持たなくても、ほかの多くの遺伝子との相互作用によって大きな関与が生み出される可能性も考えられます。
4-4-1最近話題の統合失調症の関連遺伝子
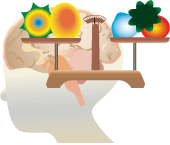
精神疾患が多く見られるスコットランドの大きな家系の研究から、DISC
(Disrupted-In-Schizophrenia)と名付けられた2つの遺伝子が注目されています。
DISC1の遺伝子は神経系の発達に関連した働きをしているようです。この遺伝子の異常がすべての統合失調症でみられるわけではありませんが、統合失調症の発症に大きな関与をするのであれば、この遺伝子の機能を探ることは統合失調症原因解明のための重要な端緒になるでしょう。これからの研究が待たれます。
動物実験から統合失調症関連遺伝子を探す試みも行われています。統合失調症のモデルとなる動物が考案されています。
このようなモデル動物の遺伝子を探ることによって、統合失調症そのものの解明にいたろうとする努力もあります。
統合失調症では、ストレスに対する弱さ、刺激に対する慣れの少なさや社会的な行動の減少がみられますので、動物で同様の症状を示すことができれば、少なくとも統合失調症の一部の症状のモデルとなるでしょう。
最近、カルシニューリン(calcineurin)という遺伝子を前頭葉だけで働かなくさせたマウスがこのような症状を示したことから、細胞内での情報伝達やタンパク質の活性化を担っているこの遺伝子の働きが注目されました。
これ以外にも、特定の遺伝子をノックアウトした(生まれつきこの遺伝子が働かなくなっている)マウスでの行動から、統合失調症の原因を考えていくという方法もとられています。
4-4-2遺伝子研究の将来
最近遺伝子治療が話題になっています。この遺伝子治療を統合失調症で行えるときがくるでしょうか。
遺伝子治療というのは、障害された遺伝子を補ったり、正常な遺伝子に取り替えたりする治療法をいいます。
しかしいまのところ、統合失調症で障害されている遺伝子が報告されているわけではありませんので、遺伝子治療はまだ統合失調症では遠い話でしょう。
しかし、薬物治療などの際に、副作用をおこしやすい遺伝子を調べることによって、副作用を予測できるようになるかもしれません。
そうなれば、その人にあったオーダーメードの治療法を、その人の遺伝子型にあわせて選択できるようになります。
さらに、この遺伝子型をもっている人は、こういう環境因子に弱いということがわかるかもしれません。
そうすると今後、その人の遺伝子型を調べることによって、発症の予防法を具体的に確立できるようになるかもしれません。
統合失調症に関連する遺伝子を研究する目的は、病気の原因となっている遺伝子を探しだし、その遺伝子の働きから統合失調症の病気の原因を調べ、さらには予防や治療をすることができるようにすることです。
現時点ではまだはっきりとした結果は得られていませんが、今後の発展が期待されるところです。

